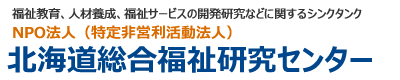「申請」という名のほったらかし
理事長 五十嵐教行
「申請」という言葉の意味について考えてみたい。
この言葉が出てくるものの一つに介護保険制度がある。被保険者が介護保険の給付を受けるためには、まず「申請」をしなければならない。「申請」の後、要介護認定へとすすみ、要介護度が判定されることになる。介護保険制度のことを知っている人なら十分に理解していることだ。本人が「申請」さえすれば、あとは流れに沿ってすすんでいくのである。つまり介護保険のシステムが動くことになる。しつこいようだが、「申請」するというところがみそだ。たとえ介護が必要な状態になっていたとしても、この「申請」がなければシステムは動かない。故にこのシステムは、「待ち」のシステムだということがわかる。
介護を苦にした虐待や殺人、心中などの事件が起こると、行政の担当者の多くがこう言う。「なぜ相談してくれなかったのか。相談さえしてくれれば、なんとかできたかもしれないのに・・・」誰か(それも行政、つまり窓口の担当者)に相談することさえ思いつかないくらい精神的に追い込まれてしまった結果の事件であることに、思いを巡らせたい。なぜ相談してくれなかったかという待ちの姿勢で、なおかつ相談を要求する姿勢ではなく、早期発見するための工夫を凝らす努力が必要なのではないだろうか。知らされてから動くというのでは後手に回らざるを得ないのである。
「申請」はまるで電化製品のスイッチのようだ。スイッチを入れるのは原則として本人である。ということは、スイッチを入れる状況にあるのかどうか、入れるとするならばいつ入れるのかといった判断を、本人がしなければならない。たしかに、ある日、劇的に要介護状態に陥った時にはこれらの判断は容易かもしれない。しかし、徐々に身体能力が落ちてきたときには、どうだろうか。どの時点から介護を必要とするのかという「線引き」を本人がすることは難しいのではないだろうか。理屈っぽく言えば、介護を必要としない状態から必要とする状態への変化について、何を基準に、あるいはどのような着目点においてチェックすればいいのかなど理解しているのかということである。介護が必要になる生活とはどういうものかということについて、極端な例を知ってはいても、ここではボーダーラインの見極めが難しいということを強く言いたい。
国の言い分は、およそ次のとおりである。自分のことを一番理解しているのは自分だ、だから本人の自己決定を尊重したい、よって本人からの「申請」が一番正しいということになる、というものだ。この言い分にも一理あるような気がしないでもない。しかし、納得できない。何故か。本人に自分のことを客観的に判断するだけの知識や情報が十分にあるとは言えないからだ。
これを読んでいただいたみなさんには、せめてこうした事実を世間話のひとつとして、たくさんの人に伝えて欲しいと心から切に願う。