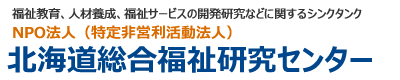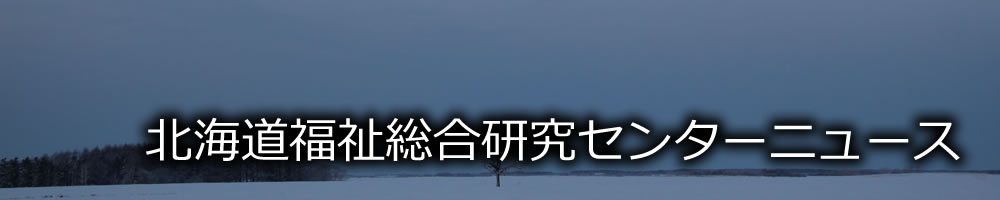巻頭言
『一富士、二鷹、三茄子』の初夢
私たちは縁起物が好きな生き物だと思う。縁起が良いものを好み、縁起が悪いものを遠ざけようとする。だから新しい年を迎えるに当たって縁起を担ぎたくなる。
そこであらためて考えたい。そもそも「縁起」とは何なのか。縁起とは、仏教用語の「因(いん)縁(ねん)生(しよう)起(き)」の略語で、すべてのものには必ずそれを生んだ因と縁とがあり、それらが複雑に影響しあって、持ちつ持たれつの状態をつくっているという意味である。つまり、あらゆるものの力や恵みなどを受けて、私たちは生かされているということになるわけだから、仏教では、縁起についての「良い/悪い」という判断はしないという。
しかしだ。それでも、私たちは幸運を招きたいと願い、縁起を担ぎたくなるのである。そして、ひたすらに吉兆のきざしを探すのだ。たしかに、縁起の悪い物や事を避けて縁起の良い物や事を選ぶ気持ちは純粋かもしれないが、自分にとって都合の良い物や事ばかりを選び取ろうとするところに人間の業の深さがあるとも感じられる。
さて、新年である。新年の縁起と言えば、やはり初夢だろう。「一富士、二鷹、三茄子」だ。これらには理由がある。
富士は、「不死」とか「無事」という言葉にかけられているし、山の形から「末広がり」の意味も込められている。鷹は、鳥の中の王として威厳ある存在であるということと「高い」という言葉にかかっている。茄子は、物事の生成や発展する様子を示す「成す」という言葉にかかっている。
実は茄子の後に「四(し)扇(おうぎ)、五(ご)煙草(たばこ)、六(ろく)座(ざ)頭(とう)」という続きがある。扇は、末広がりの形から商売繁盛や子孫の繁栄を願う意味が込められている。煙草は、煙が立ち昇る様子から幸運や運気の上昇を象徴しているという意味が込められている。座頭は、琵琶法師の座に所属する盲目の演奏家のことで、剃髪していることが特徴だ。彼らの頭には毛がなく、そこから「怪我無い」として家内安全を願う象徴とされてきたのである(筆者もスキンヘッドだから、誰かに家内安全を願う象徴として見られているのだろうか)。
このように、「一富士、二鷹、三茄子、四扇、五煙草、六座頭」には、すべて「繁栄」や「めでたさ」、「安全」などに関連する要素が含まれている。古来より人々はこれらの幸運を願う言葉に、おめでたくて幸せなイメージを重ねてながら、21世紀へと脈々と長く受け継がれて来たわけである。
私事で恐縮だが、かつて筆者は恐ろしい初夢を見たことがある。その夢の内容は、敵の組織から追われ、そして彼らに捕らえらた後、すさまじい拷問を受けるのだが、最後まで口を割らなかったのだ。どうやら私は国家のとある組織のエージェントらしい。なぜそういう夢を見たのか。スパイ映画の見過ぎだろうと思うのだが、はたしてこの夢は縁起が良いのか悪いのか、どうなんでしょう。そもそも縁起と関係あるかなぁ、あるわけないか。