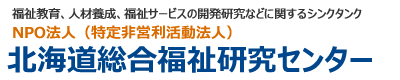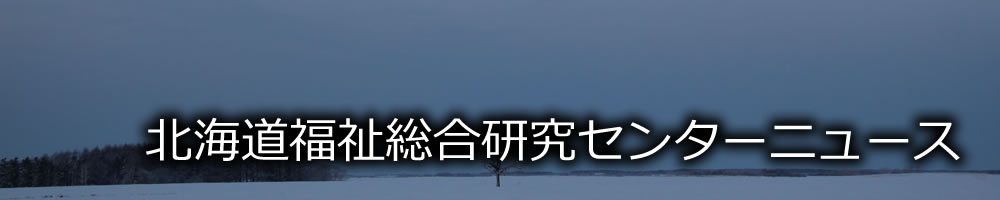巻頭言
学校の新年度のスタートが4月になった理由
私たちにとって何も違和感のない4月始まりの「年度」。そもそも「年度」が始まったのはいつからか?それは明治政府の会計年度が制度化された明治2年のことで、当初は10月始まりだった。その後1月始まりや7月始まりを経て、明治19年から4月始まりになった。4月始まりが新しい会計年度になった理由として、以下の説が有力である。
江戸時代の年貢制度が基本となったというものだ。江戸時代では幕府(領主)に年貢米を納めていたが、これが租税の基礎となる。米による現物納付を明治政府が現金納付へと変えたので、農家は米を売ったお金で納税することになった。政府は徴収した税金を元に1年間の国家予算の編成をするが、米の収穫は秋だ。税金の徴収が済んで予算編成を手がけるとなると、スケジュール的に4月始まりが妥当となったというわけである。
さて、学校における新年度のスタートが4月になった理由は次の通りである。政府の会計年度が4月始まりになると、政府から補助金を受けている学校も会計年度を4月始まりに合わせることにしたのだ。実に機械的で単純明快な理由だ。しかし、ここにもう一つの理由がある。筆者はこの理由こそが真の理由ではないかと感じるのだ。
実は4月始まりの会計年度が設定された時に「徴兵令」も改正されて、徴兵対象者の届け出期日が9月1日から4月1日に変更された。それに合わせて陸軍士官学校の入学時期が4月となった。江戸時代からあった寺子屋や藩校、明治初期の学校では入学時期等についての決まりはなかったが、明治に入って西洋式の教育制度が導入されると、一斉入学と進級が採用されるようになった。当時はドイツやイギリスの教育制度を参考にしたため、新学期は9月始まりだった。
話しを戻す。陸軍士官学校は旧制高等学校に相当するが、ある年の合格者288名のうちなんと100名がそれぞれの中学校で首席の成績者であったというから、合格者は旧制中学校での成績が上位者で占められていたといえる。陸軍士官学校の入学が4月になったことで、9月始まりだった一般の学校は優秀な学生が陸軍士官学校に流れてしまうと危惧し、それゆえ多くの学校はそれらの学生を集めるべく、4月始まりに変えていったのである。元々当時の旧制中学校への進学率は1~2割程度であったから、進学した各旧制中学校で学ぶその中でも優秀な成績を収めているかつての神童たちは、陸軍士官学校に行くかそれとも東京帝国大学に行くか、どちらにすべきかかと迷ったそうだ。
4月、桜の花びらが舞う中で入学式を迎えたという人がいる。すでに桜なんか散っていたという人もいる。どさんこである筆者は雪解けで道がグチャグチャの中を登校し、木造校舎の小学校の体育館で入学式が執り行われたことを思い出す。体育館はとにかく寒かった。1学年2クラスの小学校だったが、筆者は「1年月組」で、母親よりも年上の女性が担任だった。教室には2人用の木製の机といすで、黒板にはチョークで書かれた大きな桜の木と新幹線の絵が描かれていた。隣のクラスは「1年星組」で、筆者は自分の教室を黒板のその絵で認識して、翌日間違わずに自分の教室に入ることができた。大学生になって友人たちに「1年月組」だと話しをしたら、全員から「宝塚か!」と驚かれて、その反応に筆者は驚いた。そして気がついた。自分はなんてステキな小学校で学んだのかと。それ以来、筆者にとって「月組」に在籍していたことは、かけがえのない自慢の一つになった。